今年のはじめに、2023年の目標を100個書こうとして、いまだに75個でとまっている。
そのなかのひとつに、「本を20冊読む」という目標があるのだが、これは先月だか先々月、早々に達成した。
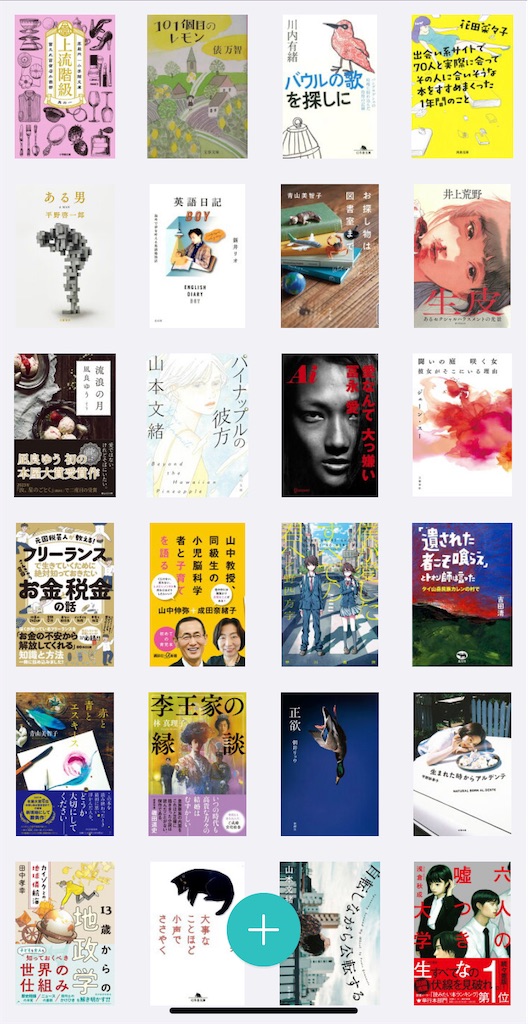
今読んでいるのは、こちら。

読んで次、読んで次……だと、内容はおろか、タイトルを見ても読んだかどうかさえ忘れてしまう。そこで、昨年頃から読書ノートをつけるようにした。
Kindleで読む時はハイライトを、本では付箋を貼っておいて、後からまとめて書き写すだけなのだけど。
読書ノートから少しばかり。

「白玉だんごはなんの味で食べようか」
健ちゃんは話を変えた。
まだ立ち直れないまま、なんとか答える。
「選ぶほどたくさん味があるの?」
「きなこを用意したんだけど、ゴマもあるし、缶詰を開ければあんこもあるよ」
「きなこでいい」
「本当に? きなこがいいの?」
「きなこでいい。どうしても聞き直すの?」
「こういうところで選ぶことの一つ一つが、生活を作るような気がするんだ。それが重なって、結局、人生になっていく。だから真剣に選ばなくちゃ」
私とおばあちゃんは午前中、おばあちゃんの希望でマタデーロスののみの市をひやかした。おばあちゃんはそういう催し事が好きだ。うきうきした、懐かしい気分になるのだという。私にはよくわからない。うきうき、となつかしい、は、全然違う気持ちだと思う。でも、おばあちゃんんくらいの年を取ると、おなじになるのかもしれない。
もし誰かが、私たちの会話を逐一筆記したものを読んだら、どこにでもある父娘の会話だと思っただろう。でも、もしそれが筆記ではなく録音とか録画だったら、自分たちの関係を喧伝しているようなものだっただろう。声には隠しようもなく歓喜や羞恥が滲んだし、見つめ合うあいだは沈黙が息づき、突発的に起こるくすくす笑いの二重奏ばかりではなく、手の動き、首の傾げ方、目の伏せ方の一つ一つまで意味を持ってしまって、つまり私たちは、食事をしながらダンスを踊っているようなものだったのだ。

半衿のお手入れ
1. 中性洗剤に水を溶かし、半衿をつける
2. 汚れがひどい場合、歯ブラシなどで布目に沿って優しくこする。その後、つけ置きをする。
3. 汚れが落ちたか確認しながら念入りにすすぐ
4. 軽く水を切って陰干しをする
5. 半乾きの頃にアイロンをかけるときれいに仕上がる
ホームシックというものがある。これは一時、人生から降りている状態である。今の、この生活は、仮の生活である、という気持ち。日本に帰った時にこそ、本当の生活が始まるのだと、という気持ちである。
勇気を奮い起こさねばならぬのは、この時である。人生から降りてはいけないのだ。成程言葉が不自由であるかも知れぬ。孤独であるかも知れぬ。しかし、それを仮の生活だといい逃れてしまってはいけない。
それが、現実であると受け止めた時に、外国生活は、初めて意味を持って来る、と思われるのです。

ぬるい風が吹き込んで、人口の葡萄の香りが部屋に満ちていく。わたしもなんだかむせそうになった。葡萄としかいいようのない、でも葡萄ではないまがいものの匂い。愛情もそうなのかもしれない。世の中に『本物の愛』なんてどれくらいある? よく似ていて、でも少しちがうもののほうが多いんじゃない? みんなうっすら気づいていて、でもこれは本物じゃないからと捨てたりしない。本物なんてそうそう世の中に転がっていない。だから自分が手にしたものを愛と定めて、そこに殉じようと心に決める。それが結婚かもしれない。
どんな痛みもいつか誰かと分けあえるなんて嘘だと思う。わたしの手にも、みんなの手にも、ひとつのバッグがある。それは誰にも代わりに持ってもらえない。一生自分が抱えて歩くバッグの中に、文のそれは入っている。わたしのバッグにも入っている。中身はそれぞれ違うけど、けっして捨てられないのだ。

──お父さんお母さんの言いつけをきちんと守りましょう。
小学校低学年までは、学校でそう教わってきた。それ以降、「もうそろそろ親を裏切ってもいい頃ですよ」とは誰も教えてはくれなかった。
「あなたがいつか親になる日がきたらわかるでしょう。子供が危険な方向へ進まない限り、自由を与えるのが最大の贐だということが」
「よくあることよ。独身の人が結婚してる人をいいなあって思って、結婚してる人が子どものいる人をいいなあって思って。そして子どものいる人が、独身の人をいいなあって思うの。ぐるぐる回るメリーゴーランド。おもしろいわよね、それぞれが目の前にいる人のおしりだけ追いかけて。先頭もビリもないの。つまり、幸せに優劣も完成系もないってことよ」
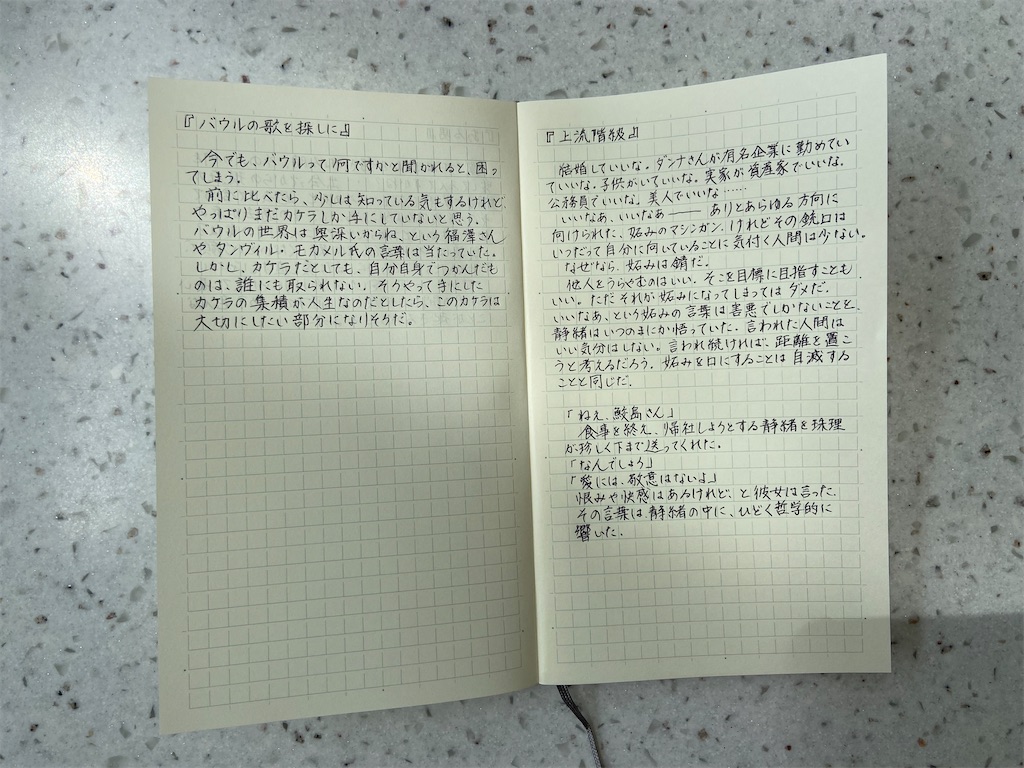
今でも、バウルって何ですかと聞かれると、困ってしまう。
前に比べたら、少しは知っている気もするけれど、やっぱりまだカケラしか手にしていないと思う。バウルの世界は奥が深いからね、という福澤さんやダンウィル・モカメル氏の言葉は当たっていた。しかし、カケラだとしても、自分自身でつかんだものは、誰にも取られない。そうやって手にしたカケラの集積が人生なのだとしたら、このカケラは大切にしたい部分になりそうだ。
結婚していいな。ダンナさんが有名企業に勤めていていいな。子供がいていいな。実家が資産家でいいな。公務員でいいな。美人でいいな……
いいなあ、いいなあ── ありとあらゆる方向に向けられた、妬みのマシンガン。けれどその銃口はいつだって自分に向いていることに気づく人間は少ない。
なぜなら、妬みは錆だ。
他人をうらやむのはいい。そこを目標に目指すこともいい。ただ、それが妬みになってしまってはダメだ。いいなあ、という妬みの言葉には害悪でしかないことを、静緒はいつのまにか悟っていた。言われた人間はいい気分はしない。言われ続ければ、距離を置こうと考えるだろう。妬みを口にすることは自滅することとおなじだ。
「ねえ、鮫島さん」
食事を終え、帰社しようとする静緒を珠理が珍しく下まで送ってくれた。
「なんでしょう」
「愛には、敬意はないよ」
恨みや快感はあるけれど、と彼女は言った。
その言葉は静緒の中に、ひどく哲学的に響いた。
カフェで本を読み、ノートを書き、コーヒーを飲む時間が、一番の贅沢。